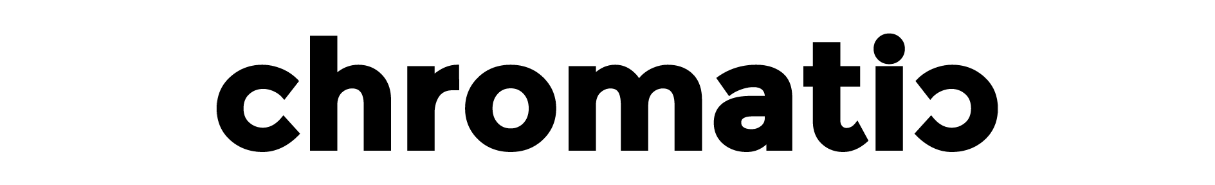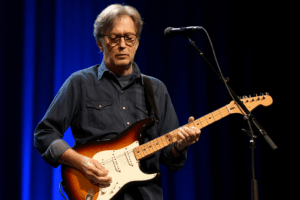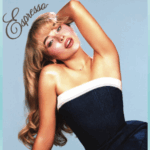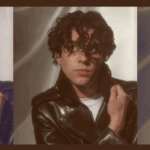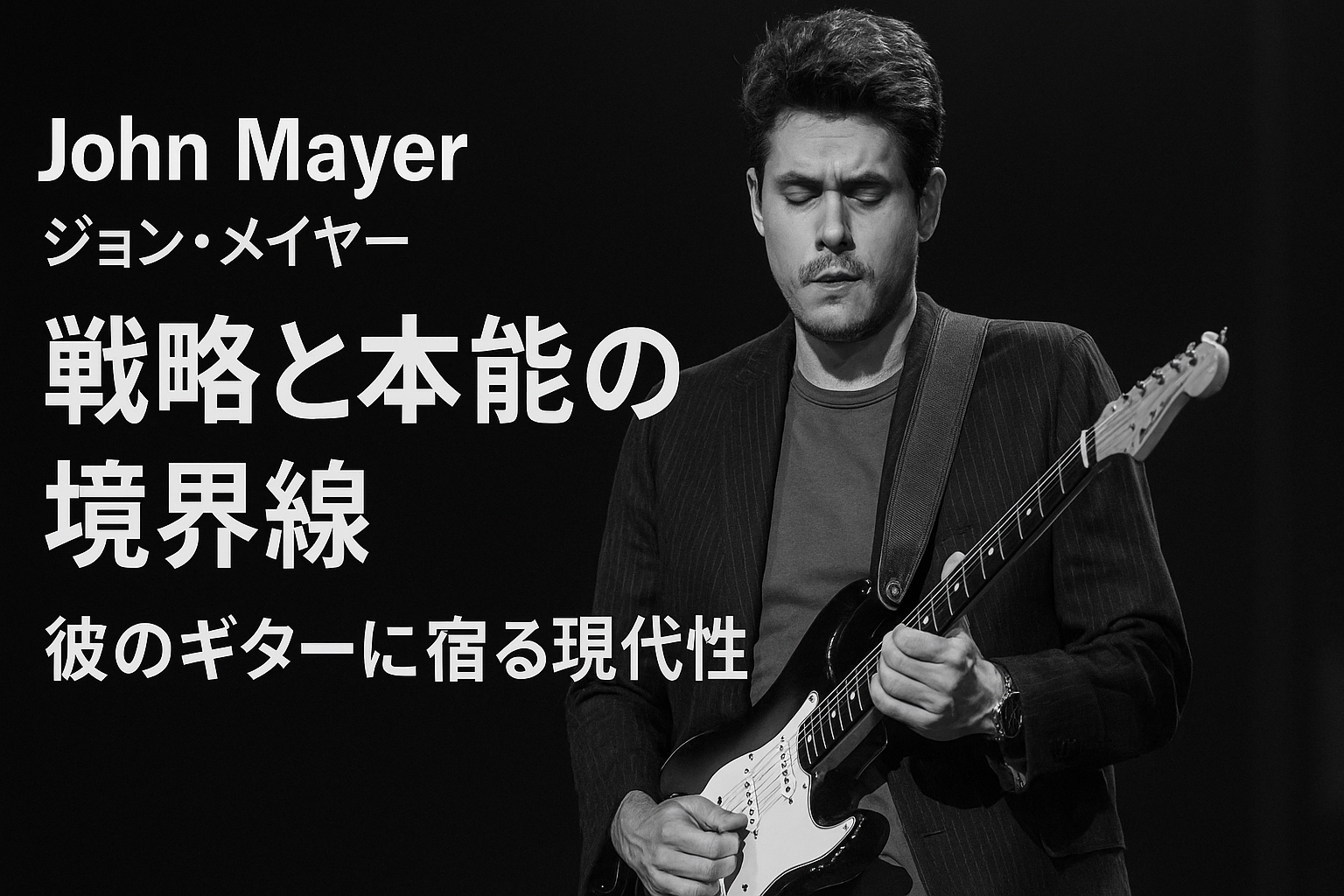
設計された“感情”に、僕らは揺さぶられる
ジョン・メイヤーのギターは、どこか冷たい。
でも、その冷たさの中に、どうしようもなく人間的なぬくもりが潜んでいる。
彼は、クラプトンやヘンドリックスの系譜として語られることが多い。
でも本質はそこじゃない。
彼は、ギターを“鳴らす”のではなく、“設計”している。
コード進行の起伏、音色の湿度、リズムの揺らぎ、空気の密度。
それらをすべて設計図に落とし込んだ上で、あたかも“偶然”弾いたかのように見せる。
その演奏は、戦略なのか?
それとも、本能か?
答えは、たぶんその“境界線”にある。
https://open.spotify.com/artist/0hEurMDQu99nJRq8pTxO14
https://www.youtube.com/watch?v=Fo4746d1L4Y
“Neon”に込められた、神経質なまでのバランス感覚
《Neon》を初めて聴いたとき、あなたは「うまい」と思うだろう。
でも、何度も聴くうちに、その“うまさ”が怖くなってくる。
ベースノートは親指で押さえ、
高音部はスラップで跳ね、
中音域はミュートしたままリズムを刻み続ける。
手の構造を完全に無視したような動き。
しかもそれを、自然に、涼しい顔でやってのける。
ジョン・メイヤーは、「ラブソングの入り口」にすら設計を持ち込む。
この徹底された“意識”こそが、彼のギターの現代性なのだ。
感情を押し付けず、“温度差”で泣かせるギター
クラプトンの音が“叫び”なら、
ジョン・メイヤーの音は“無言の視線”だ。
彼は泣かせようとはしない。
むしろ「泣くかどうかは、あなたに任せる」と言わんばかりに、感情の“余白”を残す。
《Gravity》はまさにその象徴。
重力というブルースを、彼はただそこに“置く”。
感情の起伏はない。盛り上げもしない。
でも、その無表情な音に、リスナーの心が勝手に動かされる。
それは、もはや“ギタリスト”というより、空間の設計者だ。
アンチロックスターというスタイル
ジョン・メイヤーは、ロックスターだ。
だけど彼は、ロックスターの“顔”を持たない。
SNSでは皮肉っぽく、
ライブではバンドに溶け込み、
ステージでも“語らない”ことを選ぶ。
でも、それでも彼の音は、なぜか主役になる。
「前に出ないことで、前に出る」──そんな逆説的な在り方が、
SNS時代の“疲れた耳”にちょうどいいのかもしれない。
彼はクラプトンの“痛み”を引き継ぐのではなく、
“設計と理解”に置き換えて、次の世代へとブルースを渡している。
まとめ
戦略と本能の“ど真ん中”を歩く音
ジョン・メイヤーの音は、考えてから感じる。
「美しい」より先に、「うまい」「冷静」「設計されている」と感じる。
でも、その思考の先に、ふと感情がやってくる。
クラプトンが“痛みのブルース”を弾いたように、
メイヤーは“温度差のブルース”を弾いている。
それはたぶん、現代の僕らにちょうどいい“距離感”なのかもしれない。
この記事は音楽メディア「クロマティック」によって執筆されました。