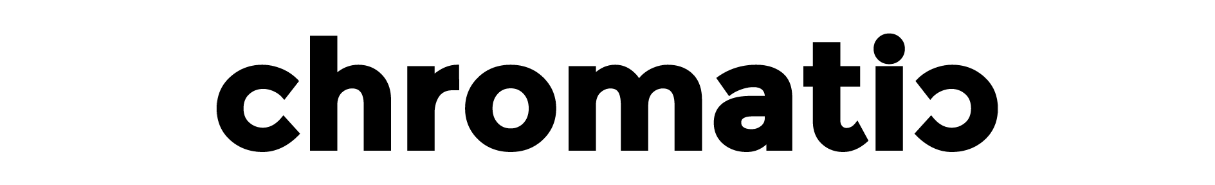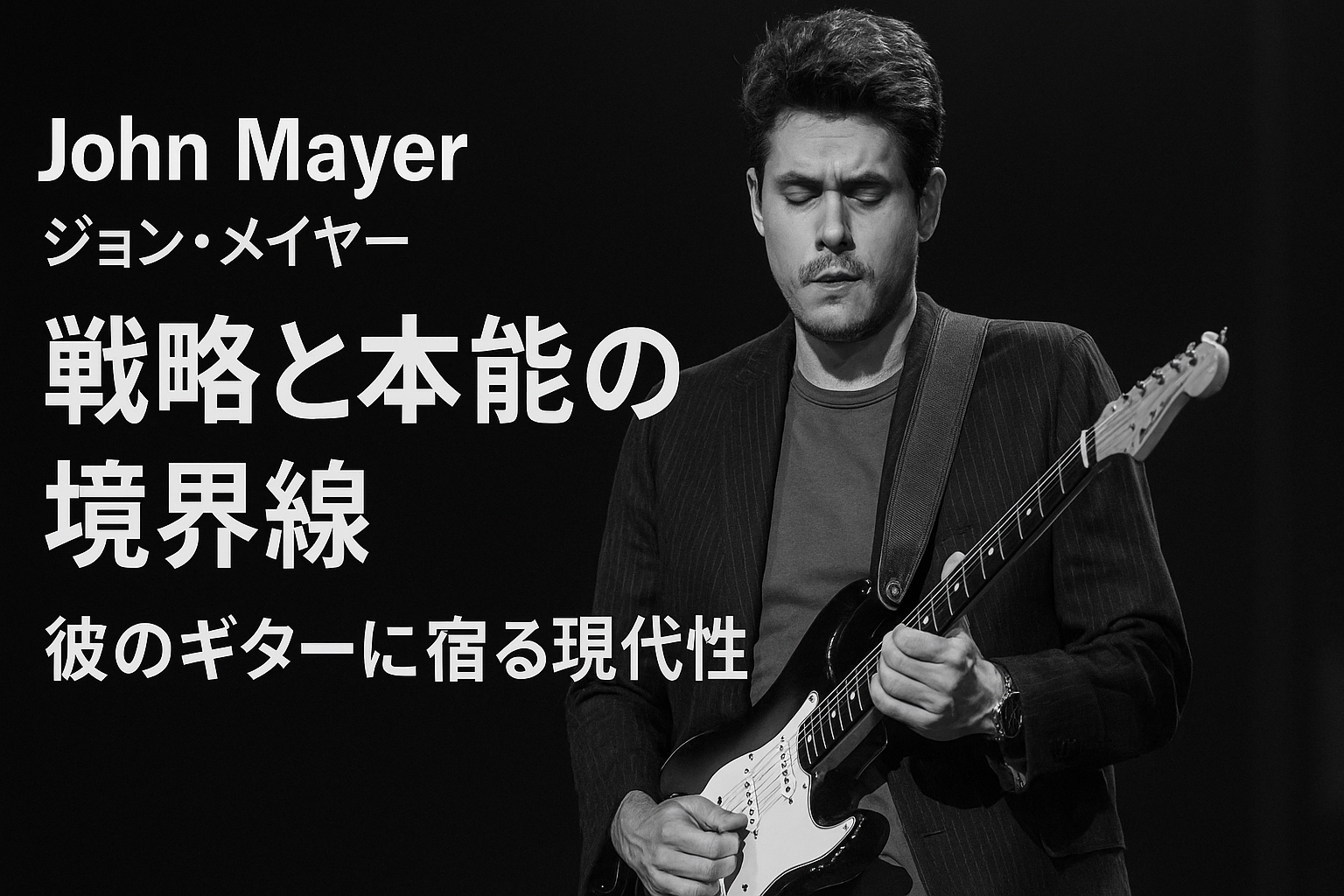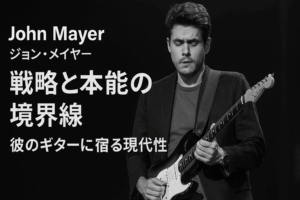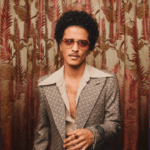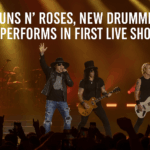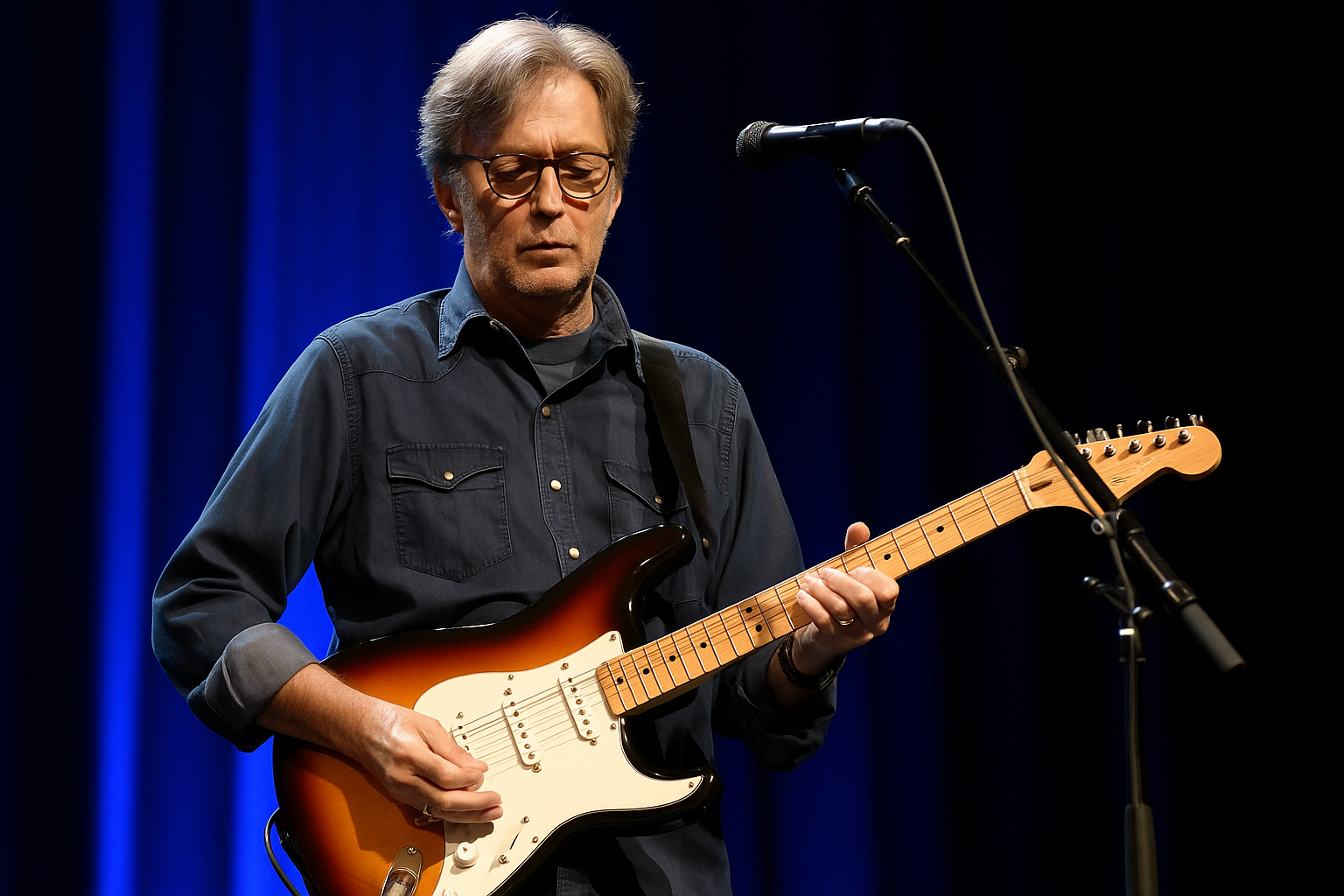
「音は、痛みの最小単位である。」
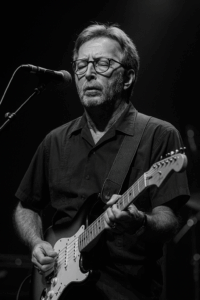
文:クロマティック編集部
▍第1章|クラプトンは“ブランド”だった。だが、本人はそれを拒んだ。
ロンドン地下鉄の壁に、かつて書かれた言葉がある。
“Clapton is God.”
“Slowhand”と呼ばれたその男は、圧倒的なプレイアビリティとブルース魂で、60年代の若者の“神”になった。
だが、クラプトン自身はその称号を嫌った。
彼の音は、むしろ──無名になりたい男の叫び。
自己否定と自己肯定が、1音ごとにぶつかり合っている。
ブランドになった瞬間から、彼の音は「語る」ことをやめ、「祈る」ようになった。
▍第2章|ブルースは“構造”ではなく“問い”である
クラプトンの音楽は、いつだってシンプルだ。
コードは3つ、スケールはペンタトニック。
だが、その“間(ま)”には──
**「人生の矛盾」**が詰まっている。
《Tears in Heaven》のコード進行は、美しい。
だが同時に、あまりにも無防備だ。
構造だけ見れば凡庸。しかし、音の“置き方”が異常に深い。
彼はコードの上にフレーズを“乗せて”いない。
むしろ、そこに**「迷い」**を残している。
これが“グルーヴ”ではなく、“間(ま)”。
そこにあるのは戦略ではなく、感情の圧縮だ。
▍第3章|クラプトンは「失敗」し続けてきたギタリストである
彼のキャリアは、チャートでは測れない。
「スーパーバンド」も何度も解散し、「ポップス」にも何度も擦り寄った。
だが、クラプトンだけはずっと“ブルース”を離さなかった。
それはジャンルではない。彼にとっての──生き残るためのプロトコルだった。
「叫びたくて、弾いた。
弾くしかなかった。」
▍第4章|戦略を持たない者だけが、“本物”を掴むことがある
クラプトンは“戦略家”ではない。
むしろ、壊れることを恐れずに、音楽にすべてを預けてきた。
その結果、残ったのが《Layla》《Tears in Heaven》《Wonderful Tonight》。
どれもが──
“本気で愛し、本気で壊れたあと”の音だ。
ビジネスの世界なら、これは“非合理”。
でも音楽においては、**「壊れた者が持つ説得力」**こそが、ブランドを超える。
▍終章|クロマティックな視点で見るクラプトン
Chromaticは、“音の隙間”を愛するメディアだ。
クラプトンのように、**「完璧じゃないことの価値」**を信じている。
彼の音楽が証明しているのは、きっとこんなことだ。
「戦略の外側に、魂はある。」
クラプトンのギターは、マーケティングでも、ポップでも、SNS映えでもない。
ただ──生きるというエネルギーが、そのまま指先に流れ込んでいた。
🎧 LISTEN THIS
🎥 Eric Clapton - Tears in Heaven (Live at Royal Albert Hall)
🎧 Spotify プレイリスト:Eric Clapton Essentials
▶ Next Article
「戦略と本能の境界線:John Mayerのギターに宿る現代性」
📝 あとがき:
#クロマティックレビュー で感想投稿もぜひ。
ギターは語らない。でも、語ってしまう何かがある。
その“間(ま)”を、私たちはこれからも読み解いていきたい。