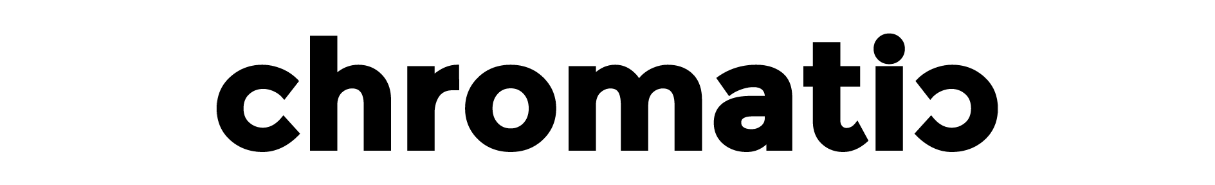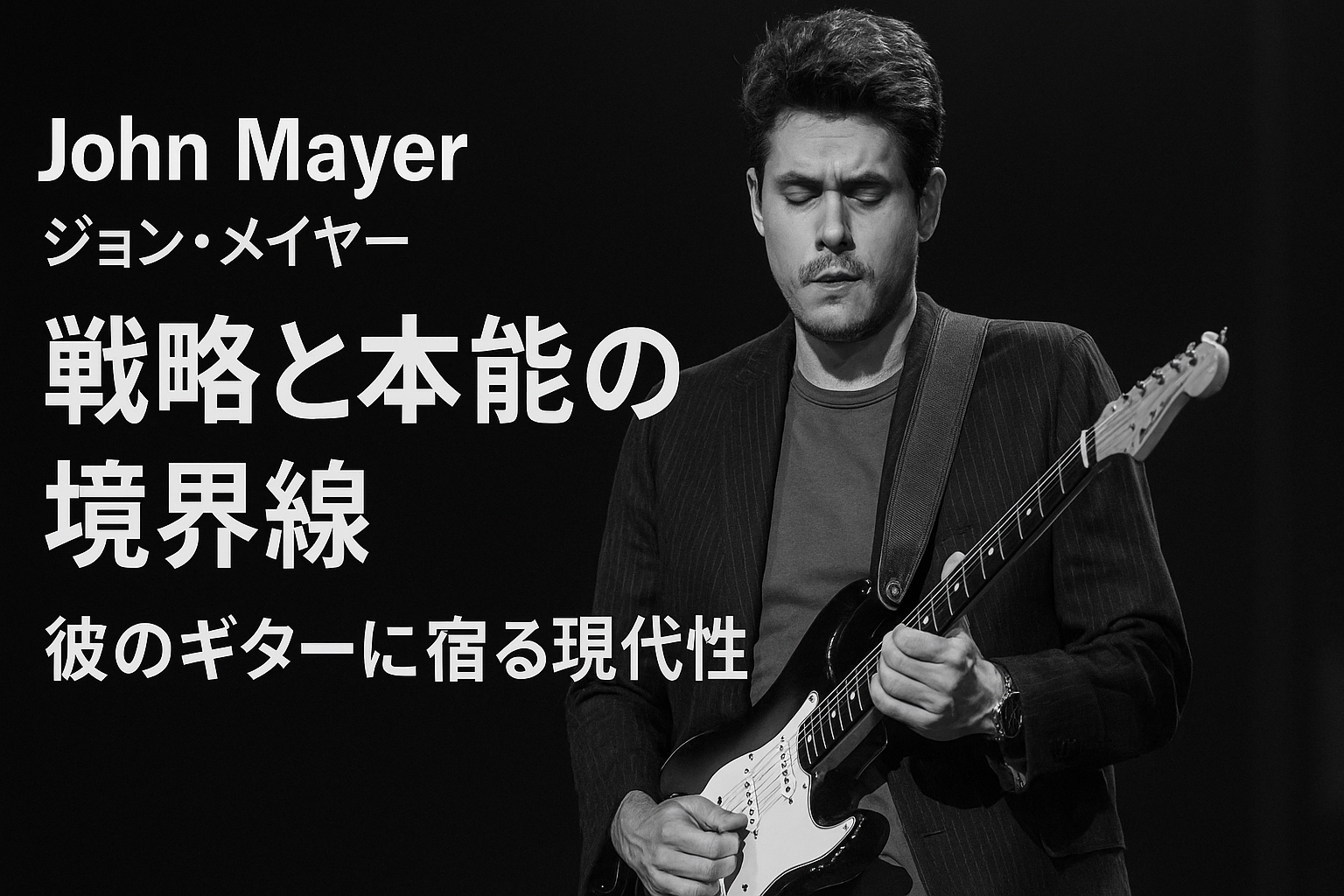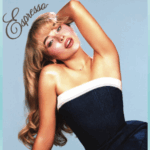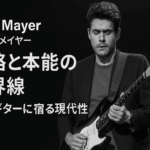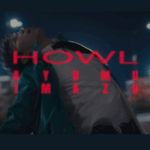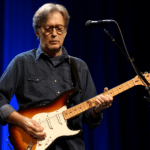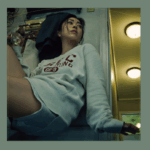売れるだけじゃ、足りない。
J-POPは変わった。
いや、変えられたと言うべきだろう。
King Gnu、米津玄師、Vaundy。
この3組は“J-POP”というジャンルを歌やメロディの次元で超えたのではない。
ポップ音楽の「設計図」そのものを組み替えてしまった。
彼らの音楽が“刺さる”のは、音が良いからではない。
構造に思想があるからだ。
そして、その思想がリスナーの「聴く姿勢」さえも書き換え始めている。
フックではなく“物語構造”で魅せる
J-POPの多くは長らく、Aメロ → Bメロ → サビの三幕構成、
あるいは「サビ始まり」のフック重視型で成立してきた。
キャッチーで一聴して覚えられる、明快な山場をつくる構成は、ヒット曲を支えてきた王道だ。
だが、彼らは“どう構成するか”そのものに意味を持たせている。
King Gnu「白日」
冒頭でいきなりサビが訪れる。
そこから徐々に情景が語られていく構成は、まるで未来を見せてから過去をたどる“回想映画”のようだ。
米津玄師「Lemon」
静かなピアノで幕を開け、言葉とメロディがゆっくりと感情を溶かしていく。
クライマックスに向けて熱を帯びていく構成は、まさに“情動のグラデーション”。
Vaundy「怪獣の花唄」
構成ごとにリズムや展開が変化し、まるで楽曲そのものが生きているかのように躍動する。
明確な転調はないが、聴感上の景色が確かに変わっていく。
彼らがつくっているのは、一曲ではなく、「時間の流れと感情の曲線」そのものだ。
音楽がシーン単位で切り取られ、消費される現代において、
サビが拡散されることすら、はじめから計算に入っている。
その構造は、単なるフックではなく、戦略であり、物語である。
ジャンルを“越える”のではなく“編む”
彼らのもうひとつの革新は、「ジャンルレス」ではない。
むしろジャンルを“引用素材”として扱う姿勢にある。
King Gnu
クラシック、ソウル、ジャズ、ハードロックを自在に編み込み、
それをバンドアンサンブルとして再構成する。演出であり、再演でもある。
米津玄師
ヒップホップ、民謡、ロック、ポップを溶かし、自身の世界観に取り込み、
詩世界の背景美術として配置する。
Vaundy
ポップスを装いながら、トラップ、シティポップ、歌謡、EDMを自由に横断し、
最終的に「Vaundyらしさ」というひとつの色に染め上げていく。
これはもはや「ジャンルを超えた音楽」ではない。
ジャンルそのものを分解し、組み直す“編集的美学”だ。
「語りかけ」ではなく、「覗き見る」歌詞
かつてJ-POPの歌詞は、“伝える”ものだった。
好き、寂しい、ありがとう――感情はまっすぐに向けられていた。
だが、彼らの歌には、少し距離がある。
King Gnu
関係性をぼかし、曖昧な視点で感情を描く。
まるで主人公の背後からそっと覗き見るような構図だ。
米津玄師
一人称は「僕」だが、それは他者に語りかけるのではなく、
自身の記憶を反芻するように紡がれる。
それは、読まれることを前提とした日記に近い。
Vaundy
自己投影しながらも、“演じる余地”と“虚構性”を残している。
そこに、感情を押し付けず、遊びとして残す余白がある。
これは「感情移入」ではなく、感情を観察し、距離をもって味わう、
新しいリスナー体験の設計と言えるだろう。
chromatic的考察
彼らはJ-POPを「壊した」のではなく、「分解した」
しばしば「J-POPを壊した」と言われるが、
彼らが実際に行っているのは、破壊ではない。
構造の解体と再構築である。
コード進行、ジャンル、詞世界、映像、そして聴かれる場面。
それらを一度すべてバラし、再び組み直すことで音楽を“設計”している。
彼らはアーティストであり、設計者だ。
彼らが示したのは、
売れる音楽は、予定調和でなくても成立する、という証明だった。
その波の先には、まだ名前のついていない
J-POPの新しい空白が、静かに広がっている。