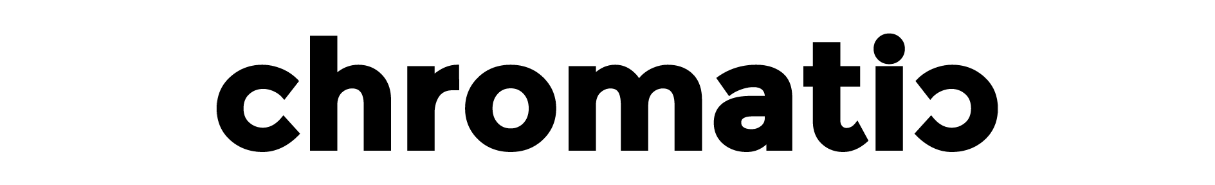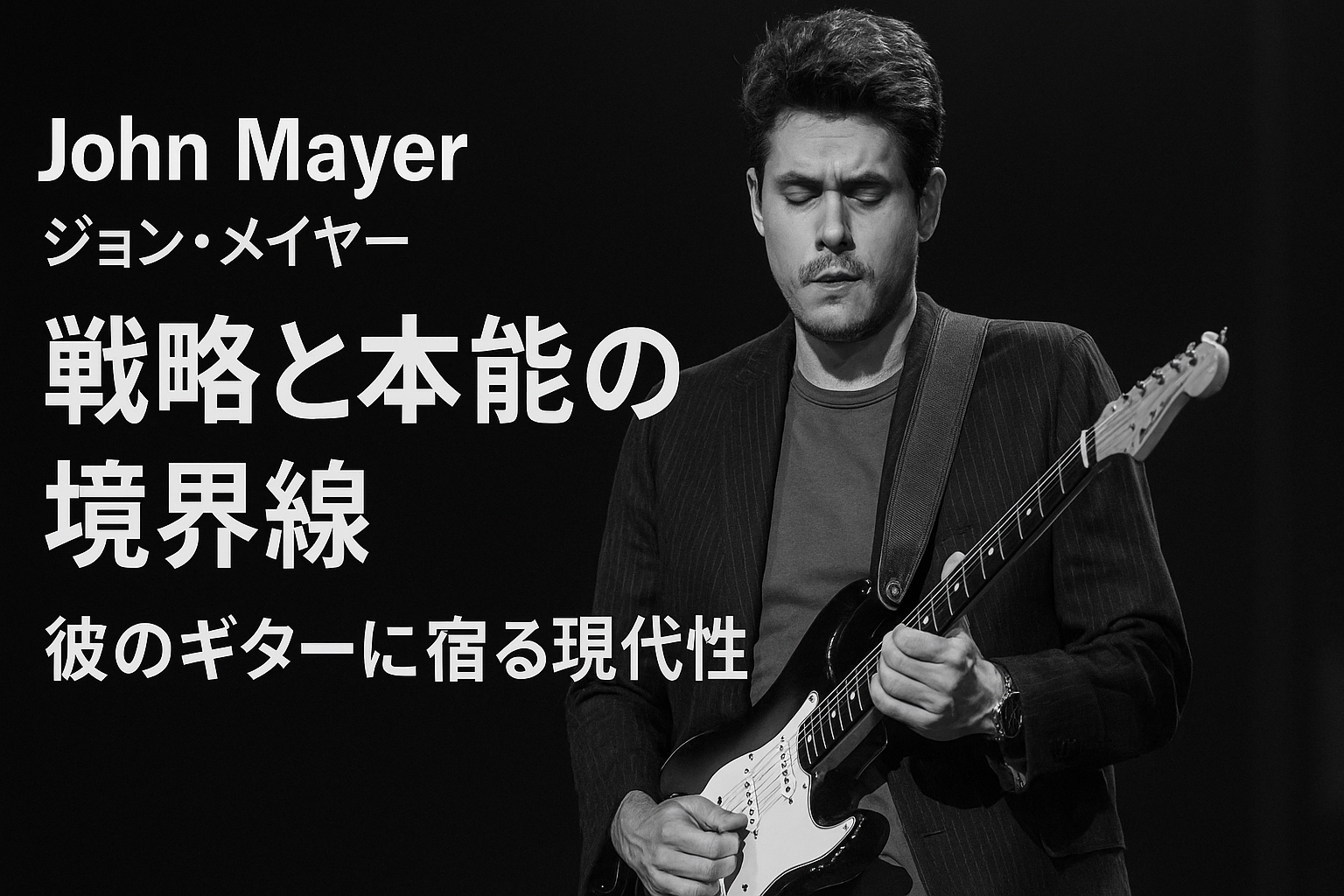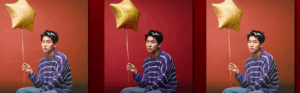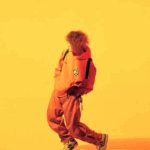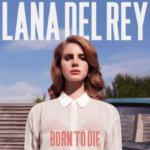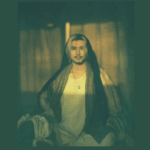彼女の歌声には、言葉では説明できない“奥行き”がある。耳に届いた瞬間に記憶を呼び起こし、今ここにない感情までも輪郭を持たせてくる。宇多田ヒカル。その名は単なるJ-POPの象徴ではなく、音楽がどれほど自由で、どれほど個人的なものであるかを証明し続ける存在だ。
革命はいつも静かに始まる
1999年、『First Love』で鮮烈なデビューを果たした当時、彼女の存在は明らかに異質だった。英語と日本語が自然に混ざり合い、R&Bを下地にしたサウンドは、それまでのJ-POPの枠組みをゆっくりと、しかし確実に壊していった。まるで異国から届いた電波のように、透明で、けれど深く響く声。その声は「わかりやすさ」ではなく、「感じる力」に訴えかける。
内省から生まれる“リアル”
宇多田の歌詞は、恋愛や人生を表層的に描かない。たとえば『Final Distance』では、喪失を描くその行間に「寄り添う」という行為の本質を託している。『Flavor Of Life』では、恋がうまくいかないことの痛みではなく、“諦める強さ”を歌っている。彼女にとって音楽とは、自己の内面に向き合うための静かな戦いであり、その軌跡がアルバムの一枚一枚に刻まれている。
『BADモード』──境界を越える音楽のかたち
2022年の『BADモード』は、これまでの集大成であると同時に、新たなフェーズへの第一歩でもある。ロンドン、ロサンゼルス、東京。複数の都市で制作された本作には、ボーダーという概念そのものが存在しない。『Somewhere Near Marseilles』のミニマルな電子音や、『Find Love』の開放的なビートは、言語も国境も越えて、「ただの音」になる。その自由さのなかに、宇多田ヒカルは“人間であること”の矛盾や脆さを見出している。
歌声は、いつも時代よりも少しだけ先を行く
彼女の音楽は、ヒットチャートを狙って作られたものではない。むしろ、チャートの「向こう側」で、時代の空気を静かに変えてきた。それは“トレンド”という名の波に乗るのではなく、自らが波になることを選んだアーティストにしかできないことだ。だからこそ彼女の音楽は、いつの時代も“少し先”にある。わたしたちはその背中を追いながら、少しずつ“聴く耳”を育てられている。
宇多田ヒカルという存在は、ジャンルでも国籍でも測れない。彼女が歌を通して示してきたのは、感情に言葉を与え、音に意味を託し、境界線の先にある“自由”を音楽で体現すること。それは、リスナー一人ひとりの“自分自身と向き合う時間”を、そっと照らす灯火でもあるのだ。