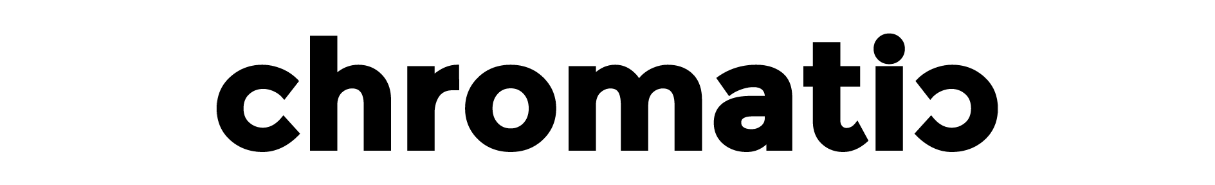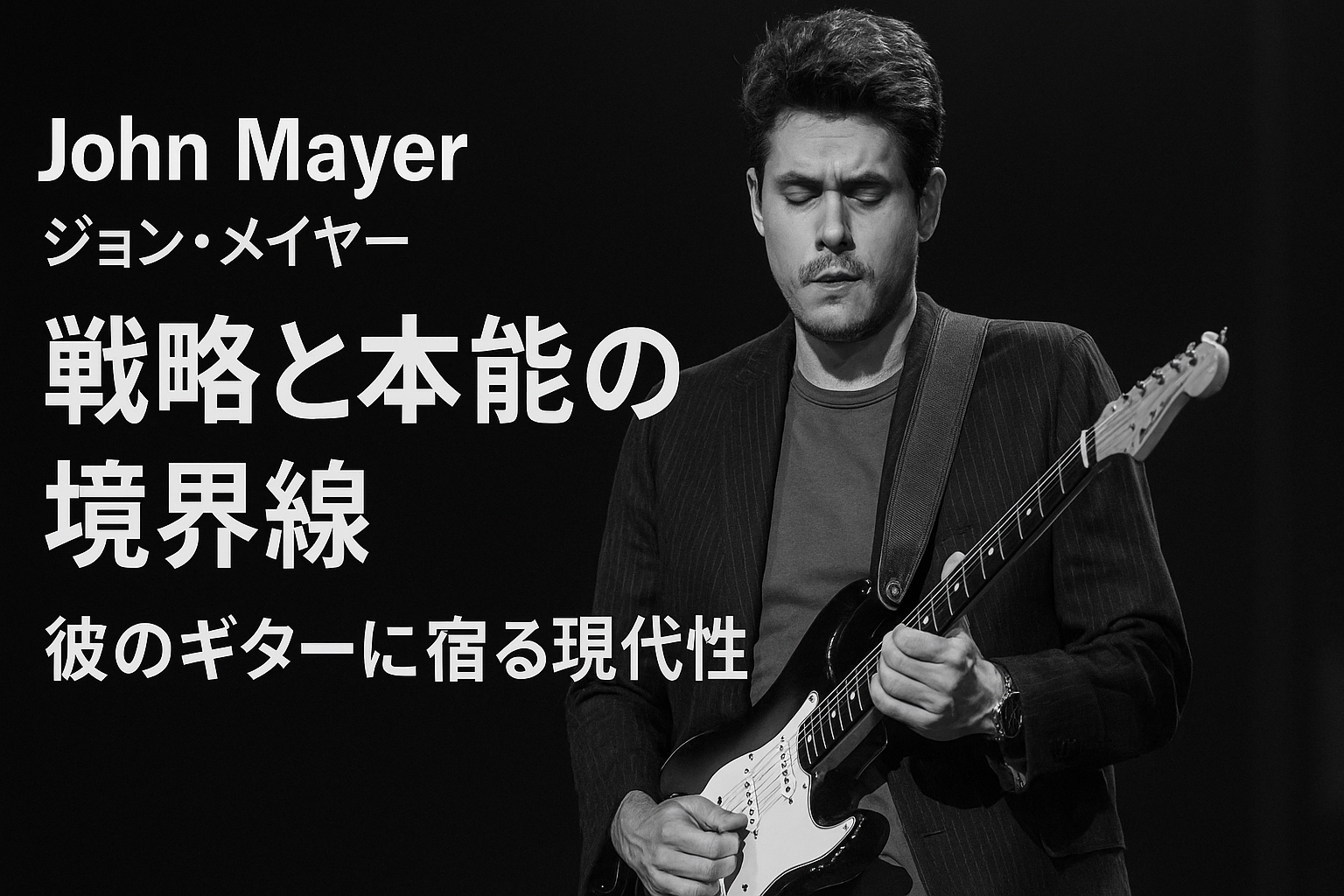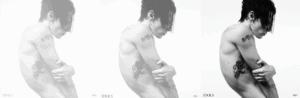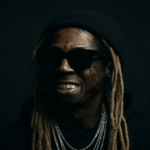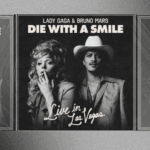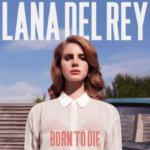一度耳にすれば、心に棲みついてしまう旋律がある。
藤井風の『死ぬのがいいわ』は、J-POPの中にありながら、その佇まいはあまりに異質だ。
過剰な装飾を剥ぎ落とした音の世界には、ただ静けさと、ピアノの余韻、そして“あの言葉”だけが残る。
ミニマルな構成が生む、音の“余白”
この楽曲には、強く訴えかけるようなサビも、テンポを変える展開もない。
あるのは、淡々と進むピアノと、絶妙な“間”──それがすべてを語っている。
藤井風は、音楽を“鳴らす”のではなく、“鳴らさない”ことで語るアーティストだ。
同じコード進行が何度も繰り返される構成は、一見単調に思えるかもしれない。
だがそれはまるで、同じ思考の渦の中を何度も回る人間の心をそのまま写したようでもある。
音の隙間が、大きな感情の起伏として立ち上がってくるのだ。
言葉の少なさが、聴き手の想像を促す
「死ぬのがいいわ」。
センセーショナルなはずのこのフレーズは、むしろ祈るような声で静かに差し出される。
意味を限定しない抽象的な言葉が、聴き手の心の奥にそっと入り込む。
ある人は恋の終わりを思い、ある人は自己肯定の希求を重ねる。
その余白こそが、この楽曲を“誰かだけの歌”ではなく、“誰にでも差し出された歌”にしている。
宗教性とポップの交差点に立つ表現者
藤井風という表現者は、宗教的な祈りとポップの軽やかさを絶妙に共存させる稀有な存在だ。
この曲の静謐さには、仏教的な無常観や“捨てる”という価値観さえ感じられる。
ただの恋の歌ではない。
これは、聴く者に“自分自身を見つめ直させる”鏡のような楽曲なのだ。
静けさこそ、最も雄弁な音
2022年から2023年にかけて、この楽曲はSNSを通じて世界的に拡散された。
英語圏のリスナーが、この曲の歌詞を「最も美しい日本語の響き」と評したように、
言語の壁を越えて心に届く何かが、そこには確かに存在する。
沈黙は、音楽の敵ではない。
ときにそれは、最も大きな音よりも雄弁だ。
『死ぬのがいいわ』は、そんな静けさの力を証明している。